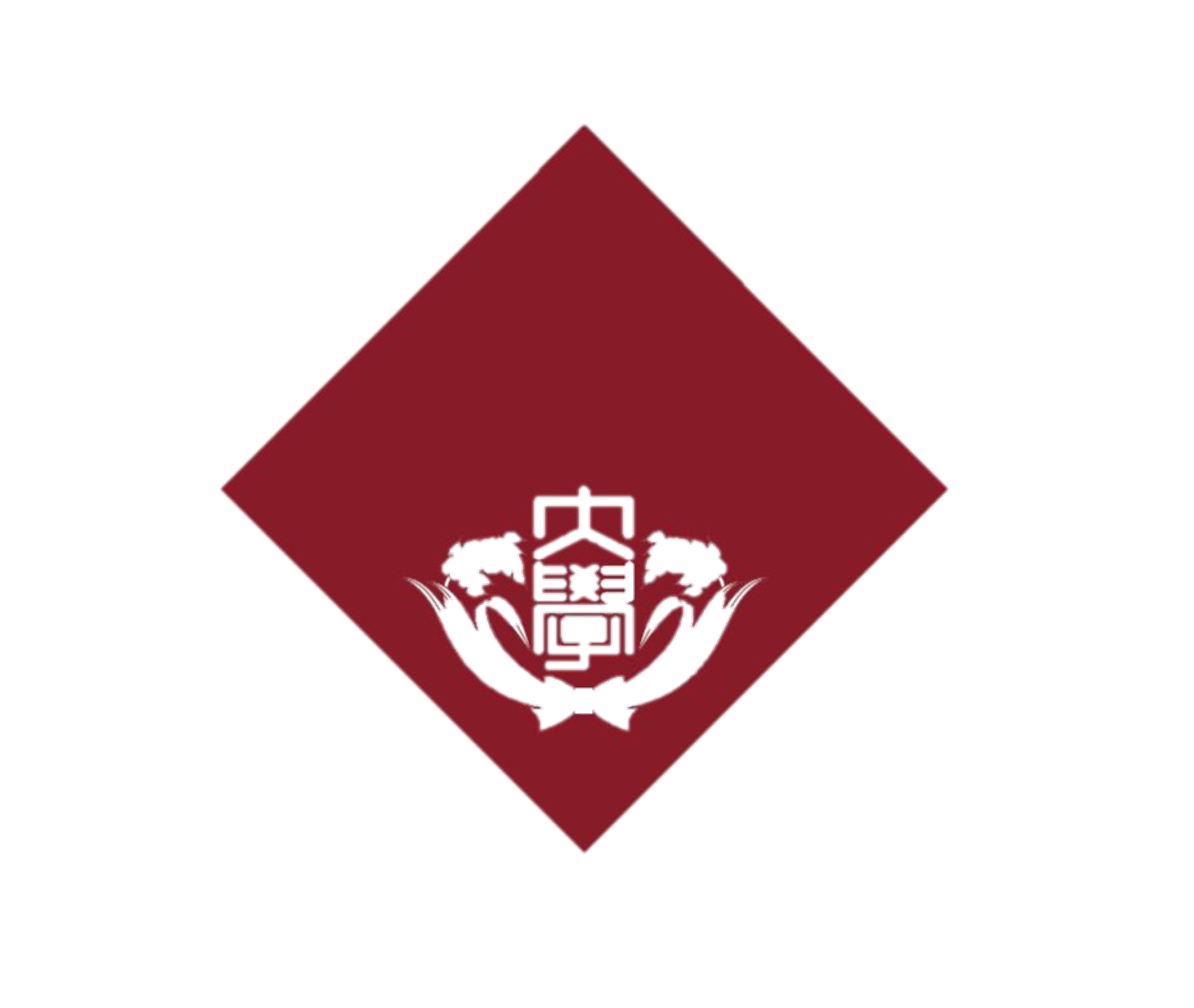受験生の皆さんへ
基幹理工学部の入試制度
基幹理工学部の入試は、日本語学位プログラムの入試(一般選抜入試、附属・系属校推薦入試、指定校推薦入試、北九州地域連携型推薦入試)と英語学位プログラムの入試に大別されます。日本語学位プログラムは学科別ではなく学系別に入試が行われ、入学後の1年間は理工系の共通科目を学び、自分の興味や適性によって2年進級時に学科を選ぶシステムです。学系別入試と進級振り分けについては、こちらをご覧ください。
よくある質問
応用数理学科で学ぶには、どの学系を受験するのが良いですか?
応用数理学科の定員は60名で、学系1から30名、学系2から15名、学系3から15名が進級できます。学系4からの枠はありません。学系2と学系3は応用数理学科に進級できる定員が少ないので、応用数理学科に進学しやすいのは学系1です。なお、数学科の学生も、英語プログラムのMath Majorの学生も、4年次に応用数理学科の研究室に配属されてゼミや卒業研究の指導を受けることは可能です。大学院では数学科と応用数理学科の区別はなくなり、数学応用数理専攻という一つの専攻になります。
数学科と応用数理学科の違いは何ですか?
数学科が数学という学問の発展を重視するのに対し、応用数理学科は「数学と数学以外のつながり」に重きを置いています。たとえば、数学を駆使した新しい機械学習手法の開発、アルゴリズムの設計と計算複雑性の理論解析、医学や生物学のデータ解析、気候予測や金融リスク評価など、数学を活用して科学・技術・産業・社会の課題を解決したい人にとっては、応用数理学科はぴったりの環境です。数学科と連携したカリキュラムで基礎数学をしっかり学びつつ、数学を他分野に応用する力を磨くことができます。
AIやデータ分析を習得したいのですが、数学をやったほうがいいのですか?
はい、AIを深く理解し、AIに関する技術を開発するには数学の知識が欠かせません。機械学習やディープラーニングの背後には、線形代数、微分積分、確率論、最適化などの膨大な理論があるからです。また、データ分析には統計学に加えて、確率論や情報理論などの知識も不可欠です。応用数理学科では、そうした数学の基礎から応用までを体系的に学び、AIやデータサイエンスの分野で本質的に活躍できる人材を多数育成しています。
応用数理に興味はあるのですが、数学の成績がそれほど良くないので心配です
数学の成績が良いことと、数学の研究ができることは、必ずしも同じではありません。応用数理学科には基礎数学から応用数学までを段階的に学べるカリキュラムが整っており、何より教育熱心な教員が揃っているため、多くの学生が成長を実感しています。もちろん高校レベルの数学はなるべくしっかり学んで欲しいですが、現在の数学の成績にとらわれて大学で数学を学ぶことを諦める必要は全くありません。
応用数理学科でもプログラミングのスキルは身につきますか?
はい、応用数理学科にはPythonやR言語やC言語やMATLABなどを使う授業や演習があります。さらに、数値解析、データ解析、アルゴリズムの実装と性能評価実験などの研究活動を通じて、プログラミングの実践的なスキルが自然と身につきます。実際、卒業研究や修士研究の研究成果をソフトウェアとして公開する学生も少なくありません。抽象的な数学の知識だけでなく、実務に必要なプログラミングの技能だけでもなく、双方を同時に習得できる稀有な環境といえます。
IT系や金融系に就職したいのですが、応用数理学科は就職に強いですか?
非常に強いです。卒業生はシステムエンジニア、データサイエンティスト、金融エンジニア、コンサルタントなどとして、IT・金融・商社・シンクタンク・官公庁などで活躍しています。応用数理で鍛えた論理的思考力・数理的分析力・実装力は、どの業界からも高く評価されています。
キャンパスの見学はできますか?
応用数理学科のキャンパスは、東京メトロ副都心線駅直結の西早稲田キャンパスです(所在地はアクセスをご覧ください)。毎年夏にオープンキャンパスが開催され、応用数理学科の教員や学生とも話せる機会になっています。オープンキャンパスに来られなくても、キャンパスの様子はYouTubeやVRキャンパスツアーでいつでも見られます。